なぜ、「大切な子ども」は地元を去ってしまうのか?

「若者の流出を食い止めたい!」— この声は、よく地域やニュースでよく耳にします。対策として「働く場の確保」「賃上げ」などが叫ばれていますが、本当にそれだけで、流出は止まるのでしょうか?
キャリア支援の観点からこの問題を見つめると、それは「単に仕事やお金だけの問題ではない」と感じずにはいられません。
特に私たち親世代は、「自分の子どもをこの地域に残したいか?」という視点から、この問題を非常にリアルに感じています。
1. 誰もが感じる違和感:若者流出を止めるための「表層的な対策」
地域が抱えるジレンマ:「50代早期退職」と「若者流出」の同時進行
今、企業では50代をターゲットにした早期退職が進んでいます。一方で、地域社会では若者流出が止まらない。
高齢化が進む地域には、長年の経験を持つベテラン層(40代・50代・60代)が潜在的にいるにもかかわらず、その方々の「働く場」も「再活躍の場」も少ないのが現実です。
若者を呼ぶこと、定着、流失ばかりに注力し、今地域にいる人材や、やむなくリタイアした人材を有効活用できていない。このアンバランスさが、地域全体の活力を低下させているのではないでしょうか。
「お金を積めばいい」という単純な解決策への疑問
もちろん、賃金は重要です。しかし、「賃金を上げれば若者は残る」という考え方は、地域の持つより本質的な問題を見えなくしている気がします。
私たちが本当に心配なのは、子どもたちが「自分の未来がこの地域で見えない」と感じてしまうことではないでしょうか。
2. 若者が戻らない、最大の理由:活用されない「地域の宝」
先日、地元から都心で長く活躍されていた若い方が、Uターンで戻ってこられた時のエピソードを聞きました。その方は、こんな風に感じたそうです。
「地域に戻ってみて、新しいことを取り込もうとしない雰囲気と、既存の人材が有効活用されていない現実に、強い閉塞感を感じました。ここでは自分の成長が止まってしまう。やはり都心に戻ることを決めました。」
彼らが求めているのは、「自分の能力や新しいアイデアが活かせる場があるか」、そして「世代や肩書きに関係なく、地域をより良くしていこうという熱意と仕組みがあるか」、ということ。
高齢化が進む地域でこそ「全世代の才能」を生かせ
ベテラン層から若者まで、地域にいるすべての人材を「地域の宝」として捉え直す視点が必要です。
- 長年の経験を持つ方々が、新しい事業を始める若者のメンターになる。
- ベテランが持つネットワークと、若者の新しい技術や視点を組み合わせる。
「人口割合を見て、その構成を生かす方向性が違う」というキャリア育成に携わる方の意見は、本質を突いています。若者だけを特別扱いするのではなく、地域全体の才能を循環させる仕組みこそが、活力を生むのではないでしょうか。
3. 私たちのキャリア支援の視点:未来の「体温」を上げるために
子を持つ親として、私たちは自分の子どもに「未来を感じられる場所」を残したいと心から願っています。若者が流出しない地域とは、単に「仕事がある」場所ではなく、「未来への期待」という体温が高い場所です。
地域の「担い手」として一歩踏み出す
私たちようなベテラン層が、自身のキャリアチェンジとして地域での新しい活動に参加してみるのも一つの方法です。
「早期退職」を単なるリストラと捉えるのではなく、「地域を再構築する担い手」として、自らの経験やスキルを、既存の組織ではない場所で活かし始めるのです。そういう働き場の確保も必要かと感じました。
子どもに「希望」を感じさせる地域の大人になる
子どもたちに「ここに残ってほしい」と口で言うだけでなく、地域の大人たちが、楽しそうに、そして前向きに挑戦している姿を見せることが、何よりのメッセージになります。
「失敗を恐れず、新しいことを受け入れる柔軟な雰囲気」を私たち自身が作り出すことが、若者が「ここは面白い」「自分も成長できる」と感じる土壌になるはずです。
若者流出の問題は、私たち全世代のキャリアと生き方に直結しています。
単なる「賃金アップ」を求めるだけでなく、「自分の未来、そして地域の未来に期待が持てる仕組み」を、作ることが必要だと感じました。
移住定住成功の鍵:「住みやすさ」から「生き生きと働く場所」へ
単なる「子育てしやすい街」では、人は長く定着しない
多くの自治体が移住定住策として「子育て世代の優遇」や「住みやすさ」を重要視します。確かに、それは移住の初期段階では重要です。
しかし、子育てを終えた後、移住した人自身が「長くそこで生き生きと働き続けられる場所」がなければ、子どもが成長した途端、また都市へ流出してしまうことになります。
移住者にとって本当に大切なのは、「自分のスキルが地域で活きるキャリアの選択肢があるか」、そして「地域の一員として、年齢や肩書きに関係なく楽しさを感じられる居場所があるか」なのです。
子どもたちが将来を見据えたとき、「ここに自分の能力を活かせる仕事がある」「この地域の大人たちは生き生きと楽しそうに働いている」と感じられること。
高齢化が進む地域こそ、人材活用の最前線へ
親世代が、ここにいても仕事がないと感じる環境をもたらすことが流失にもつながる。
年齢を重ねても、これまでの経験を活かせる仕事があり、親世代が長く楽しく定着している。そんな活気ある姿は、若い世代の子どもたちにとって「この地域で生きる未来」に対する最大の安心感と、揺るぎない希望を感じてくれるのではないかと感じます。

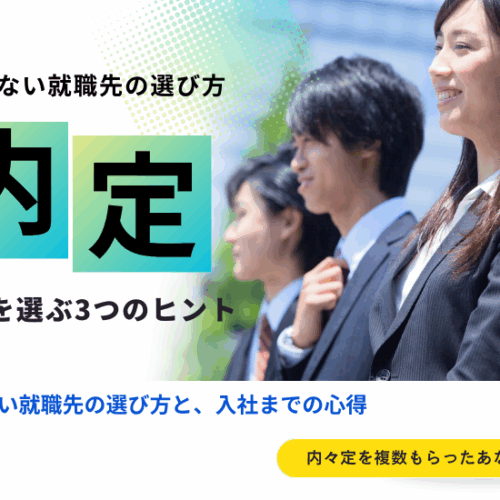


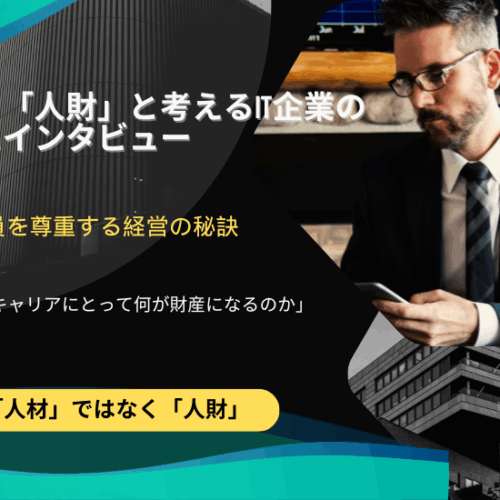
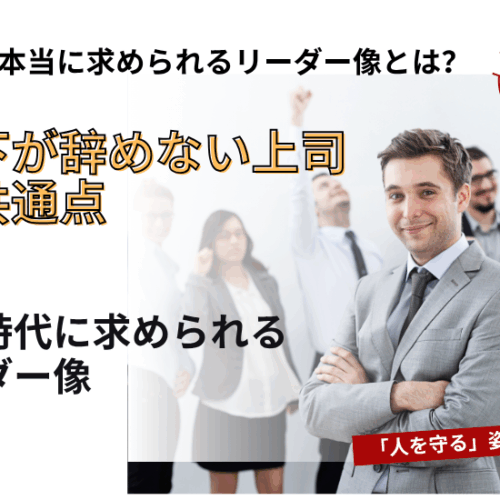


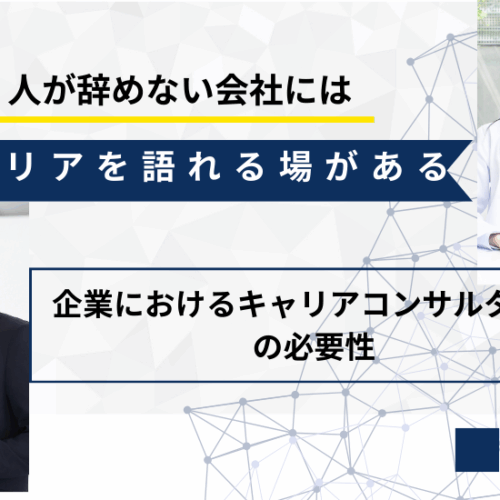
この記事へのコメントはありません。